先頭固定
2026年2月23日 この範囲を時系列順で読む
Switch版「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」をクリアしたよ
Switch版「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」をクリアしたよ
面白かったぞ~~~~~~~~~~。
https://www.jp.square-enix.com/paranorma...
前作「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」(感想記事・58)を遊んで楽しかったんで、続編発表されてからウキウキしながら待ってました。2週間だけど(初報から2週間で発売された)
1980年代の日本、三重県伊勢地方に残る伝承を元に「人魚」を探す群像劇アドベンチャー。それぞれの目的に沿って人魚を探す4組のコンビを操作しながら、この地域に伝わる人魚伝説の真相に迫るというもの。
前作も東京墨田区「本所」に伝わる怪談をベースにしつつ、その実「特殊能力を得た現代人たちが、互いの命を狙いあう」というバトルロワイヤル形式が含まれていましたが、今作はその辺は大きめにオミット。目の前の事件や伝承を探るミステリーの趣がより強くなっています。ただ前作にもあった「腹の探り合いバトル」も、これはこれでばっちりあるぞ。
後はよく言われますけどホラー要素がかなり減らされており、その点でも広く遊びやすくなっていると感じました。なお、ホラー要素がないとは言ってない。
いわゆるジャンプスケア系の演出が減らされただけで、スプラッタ演出やじわっとした怖がらせは全然あるし、なんなら今回ははっきりと怪異にもスポットが当たっているせいなのか、猟奇要素てんこもりで自分はこっちの方がしんどい。
ともあれ、「選択型のノベルゲーム」をベースに、よくこんなギミック盛り込んだね???? と大混乱も必死のゲーム的トリックが、面白くもあり歯ごたえもあり。たぶんすべての人が言及すると思うんですけど、自分も最後のあれはほんっとにわからず1時間近くゲーム画面をうろうろして、よーやく見つけていたし、見つけた瞬間の「すべて」が繋がる感触に感服しました。この感動はねー、ほんとにパラノマサイトさん様様です。
あとはなんといってもキャラクターたちの妙が冴えわたっている。前作では命のやり取りも踏まえたシリアスでおどろおどろしい雰囲気ながらに、絶妙に珍奇なことをいうキャラクターたちが清涼剤になってましたが、本作ではよりパワーアップ。舞台上の重苦しい空気がない分、キャラクターたちのトンチキさにブレーキがかからずずっと楽しい。
それでいて、珍奇なキャラクターたちに気持ちを寄せられないかというと、そんなことはなく。みんな気持ちのいい性格をしていたり、気持ちを寄せられる余地があったりと丁寧なキャラ造形が素晴らしい。前作の感想記事でも「ずっとこの会話聴いてたいなあ」と書いてたんですが、それがまさに叶っていて大満足です。
ここからは本編の内容に踏み込んだ話をしていきますよ。
前作との比較になりますが、前作の本所七不思議ではある瞬間に一斉に特殊能力が発現し、一斉に登場人物らが動き出すことで物語が動きましたが、本作の伊勢人魚物語はむしろ「そこにいる人の過去にさかのぼって、なぜそこにいるのかを探る」という向きが強い。
一見すると、本作の構造が時系列が複雑でプレイヤーの把握を難しくする要因に思えますが、実際には本作のテーマ性に根差した構造なのだろうとクリアした今なら感じます。そこにいる人にはそこにいる人なりの人生や歴史があるし、そこにある史跡や伝承も同じ。
本作では1980年代・鎌倉時代・平安時代という3つの時代におきた事件がキーとなっていますが、それらは断絶した事象ではなく、すべて今の伊勢地方を構成する重要な要素なんですよね。鎌倉時代の事件も平安時代の事件も、現代から見れば「昔話」としてひとくくりにしがちですが、実際には鎌倉時代の伝承は平安時代の歴史を踏まえて展開されたものだったりして、そこには連綿と続く人の営みがあったから今にも続いている。
いくつもの歴史が重なり合って現代に、そして未来に通じていくという本作のテーマ性と、登場人物らの過去に遡って経緯を知ることで真相に迫るゲーム性は密接に関係しているし、すべてのピースが見つかってひとつながりになって見えた時の感動はたまらないものがありました。
個人的に気に入ってる点に、本作では「常人ではなくなるもの」が描かれますが、だからといって人ではなくなることの悲しみが描かれるわけでもなく、「生きててサイコー」という人生の謳歌だったことが好きです。ひと、すぐに「人間が最高、人間じゃなくなるのは最悪」にしがち。でも人間じゃなくったって幸せもあるだろうし、そいつにはそいつの筋ってもんがあるよな、と軽やかに描いてくれて嬉しい。
楽しかったぞー。
コミックス版「パラノマサイト FILE25 霊感少女・黒鈴ミヲの邂逅 」を最高なのでぜひ。
面白かったぞ~~~~~~~~~~。
https://www.jp.square-enix.com/paranorma...
前作「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」(感想記事・58)を遊んで楽しかったんで、続編発表されてからウキウキしながら待ってました。2週間だけど(初報から2週間で発売された)
1980年代の日本、三重県伊勢地方に残る伝承を元に「人魚」を探す群像劇アドベンチャー。それぞれの目的に沿って人魚を探す4組のコンビを操作しながら、この地域に伝わる人魚伝説の真相に迫るというもの。
前作も東京墨田区「本所」に伝わる怪談をベースにしつつ、その実「特殊能力を得た現代人たちが、互いの命を狙いあう」というバトルロワイヤル形式が含まれていましたが、今作はその辺は大きめにオミット。目の前の事件や伝承を探るミステリーの趣がより強くなっています。ただ前作にもあった「腹の探り合いバトル」も、これはこれでばっちりあるぞ。
後はよく言われますけどホラー要素がかなり減らされており、その点でも広く遊びやすくなっていると感じました。なお、ホラー要素がないとは言ってない。
いわゆるジャンプスケア系の演出が減らされただけで、スプラッタ演出やじわっとした怖がらせは全然あるし、なんなら今回ははっきりと怪異にもスポットが当たっているせいなのか、猟奇要素てんこもりで自分はこっちの方がしんどい。
ともあれ、「選択型のノベルゲーム」をベースに、よくこんなギミック盛り込んだね???? と大混乱も必死のゲーム的トリックが、面白くもあり歯ごたえもあり。たぶんすべての人が言及すると思うんですけど、自分も最後のあれはほんっとにわからず1時間近くゲーム画面をうろうろして、よーやく見つけていたし、見つけた瞬間の「すべて」が繋がる感触に感服しました。この感動はねー、ほんとにパラノマサイトさん様様です。
あとはなんといってもキャラクターたちの妙が冴えわたっている。前作では命のやり取りも踏まえたシリアスでおどろおどろしい雰囲気ながらに、絶妙に珍奇なことをいうキャラクターたちが清涼剤になってましたが、本作ではよりパワーアップ。舞台上の重苦しい空気がない分、キャラクターたちのトンチキさにブレーキがかからずずっと楽しい。
それでいて、珍奇なキャラクターたちに気持ちを寄せられないかというと、そんなことはなく。みんな気持ちのいい性格をしていたり、気持ちを寄せられる余地があったりと丁寧なキャラ造形が素晴らしい。前作の感想記事でも「ずっとこの会話聴いてたいなあ」と書いてたんですが、それがまさに叶っていて大満足です。
ここからは本編の内容に踏み込んだ話をしていきますよ。
前作との比較になりますが、前作の本所七不思議ではある瞬間に一斉に特殊能力が発現し、一斉に登場人物らが動き出すことで物語が動きましたが、本作の伊勢人魚物語はむしろ「そこにいる人の過去にさかのぼって、なぜそこにいるのかを探る」という向きが強い。
一見すると、本作の構造が時系列が複雑でプレイヤーの把握を難しくする要因に思えますが、実際には本作のテーマ性に根差した構造なのだろうとクリアした今なら感じます。そこにいる人にはそこにいる人なりの人生や歴史があるし、そこにある史跡や伝承も同じ。
本作では1980年代・鎌倉時代・平安時代という3つの時代におきた事件がキーとなっていますが、それらは断絶した事象ではなく、すべて今の伊勢地方を構成する重要な要素なんですよね。鎌倉時代の事件も平安時代の事件も、現代から見れば「昔話」としてひとくくりにしがちですが、実際には鎌倉時代の伝承は平安時代の歴史を踏まえて展開されたものだったりして、そこには連綿と続く人の営みがあったから今にも続いている。
いくつもの歴史が重なり合って現代に、そして未来に通じていくという本作のテーマ性と、登場人物らの過去に遡って経緯を知ることで真相に迫るゲーム性は密接に関係しているし、すべてのピースが見つかってひとつながりになって見えた時の感動はたまらないものがありました。
個人的に気に入ってる点に、本作では「常人ではなくなるもの」が描かれますが、だからといって人ではなくなることの悲しみが描かれるわけでもなく、「生きててサイコー」という人生の謳歌だったことが好きです。ひと、すぐに「人間が最高、人間じゃなくなるのは最悪」にしがち。でも人間じゃなくったって幸せもあるだろうし、そいつにはそいつの筋ってもんがあるよな、と軽やかに描いてくれて嬉しい。
楽しかったぞー。
コミックス版「パラノマサイト FILE25 霊感少女・黒鈴ミヲの邂逅 」を最高なのでぜひ。
2026年2月19日 この範囲を時系列順で読む
心がヘロヘロしているんだ
心がヘロヘロしているんだ
なんかまだ体調がぐにゃんぐにゃんしており、辛うじて最低限文化的な社会生活は送れているんだけども、ちょっとでもはみ出た部分はもうなんかぐっちゃぐちゃでどうしようもない。
風邪ひいたときにうっかり寝不足も重ねたのが利いてるみたいで、風邪症状はなくなったのにずーっと眠気と倦怠感が続いている感じです。その割に寝つきが悪くて寝不足のループ。
ちょっと世間が温かくなってきたのもあるかな~。季節の代わり目に身体が追いつかないやつ。地元ではこの時期に葬式が増えます。わいはまだ生きる。
なんかまだ体調がぐにゃんぐにゃんしており、辛うじて最低限文化的な社会生活は送れているんだけども、ちょっとでもはみ出た部分はもうなんかぐっちゃぐちゃでどうしようもない。
風邪ひいたときにうっかり寝不足も重ねたのが利いてるみたいで、風邪症状はなくなったのにずーっと眠気と倦怠感が続いている感じです。その割に寝つきが悪くて寝不足のループ。
ちょっと世間が温かくなってきたのもあるかな~。季節の代わり目に身体が追いつかないやつ。地元ではこの時期に葬式が増えます。わいはまだ生きる。
2026年2月12日 この範囲を時系列順で読む
メンタルのヘルスがへろへろ
メンタルのヘルスがへろへろ
ぜったいこれ季節柄だよなあと。去年の今頃のこの日記にもへろへろ期の記録が残ってるんですが、このくらいの時期が一番不安定。寒いし暗いしたまに暖かいしで外が不安定だと自分も不安定です。
こういう時は自分の将来だとか、社会情勢だとか、気候変動だとかを憂いてひたすら悲しく憤って身動きが取れなくなるんですけど、身動きが取れなくなるのが悪いんであってそういうことを考えること自体は悪いことじゃないんだぞと言い聞かせてます。だから猶更つかれてへろへろすんのかな。
ぷえー。
ぜったいこれ季節柄だよなあと。去年の今頃のこの日記にもへろへろ期の記録が残ってるんですが、このくらいの時期が一番不安定。寒いし暗いしたまに暖かいしで外が不安定だと自分も不安定です。
こういう時は自分の将来だとか、社会情勢だとか、気候変動だとかを憂いてひたすら悲しく憤って身動きが取れなくなるんですけど、身動きが取れなくなるのが悪いんであってそういうことを考えること自体は悪いことじゃないんだぞと言い聞かせてます。だから猶更つかれてへろへろすんのかな。
ぷえー。
2026年2月6日 この範囲を時系列順で読む
ぜんぜん元気
ぜんぜん元気
鼻がじるじるだし、リンパ腺が腫れてちょっと熱っぽいけど全然風邪じゃない。
数日前にメンタルが不安定でやば〜と思ってたら、多分あれ風邪の前兆だったんだろうな。全然風邪じゃないけど。
ネット断ちと言いつつ、予定してた更新などで結局ネットにはいたんですが、更新終わったらすぐ離れてバタッと倒れるみたいな日々です。もしかして風邪かもしれない。
ニンダイをチラチラ見ていたのですが、「一時期のスクエニは野村or直良氏の絵ばかりだったが、近年は生島氏のターンなんだなあ」と思ってました。評価されて勢いのあるチームがわかりやすすぎる。
鼻がじるじるだし、リンパ腺が腫れてちょっと熱っぽいけど全然風邪じゃない。
数日前にメンタルが不安定でやば〜と思ってたら、多分あれ風邪の前兆だったんだろうな。全然風邪じゃないけど。
ネット断ちと言いつつ、予定してた更新などで結局ネットにはいたんですが、更新終わったらすぐ離れてバタッと倒れるみたいな日々です。もしかして風邪かもしれない。
ニンダイをチラチラ見ていたのですが、「一時期のスクエニは野村or直良氏の絵ばかりだったが、近年は生島氏のターンなんだなあ」と思ってました。評価されて勢いのあるチームがわかりやすすぎる。
2026年2月1日 この範囲を時系列順で読む
目に入るすべての情報に対して意見いいたくなってる
目に入るすべての情報に対して意見いいたくなってる
たぶんメンタルが疲れてる。
わたくし、二十世紀末から四半世紀ほどネットを毎日徘徊しているにわかネット民なんですが、その辺から「目に入った誰かの発言に物申したくて仕方ない」という癖があるという自覚がありまして。その中身は、別に相手の意見を徹底的に否定したいわけでもなく、「そうだよねーわかるー私はねえ」と肯定のように見えて話題を勝手に乗っ取るという、かなり厄介な傾向があります。
「この考え方ヤバいな」と感じている自分もいるので、普段はある程度抑えこんでいる(抑え込んでいるよね?)のですが、何かの拍子にぶわーっと表出するときがある。
自分としてはなんだろな、赤ん坊が目に入ったものとりあえず口に入れてみて試すみたいな、あれに似てるなと思っている。目に入ったもの耳に入るもの、例えば街中の広告とか、となり歩いてる人たちの会話だとか、普段なら脳内で「ないもの」と処理されるのにこの時だけは「あるもの」の箱に片っ端からいれちゃって自動で処理が始まる感じ。最初は気づかないけど気づけば普段以上の負荷がかかって頭がぐるぐると回り出して変になってくる。
そういう衝動、ネットのおかげでWEB日記やブログに書いたりすることで発散していた時期もあるんですが、「それ関わらん方が絶対いいよ」ってやつにも食いついちゃうので、サイクルの速いSNSの世の中とは本当に相性が悪い。
急に「それ」がきたので、その発散と、宣言としてこれ書いてます。数日ネットみません。見ないっつっても数日だけだからネット廃人ほんとよくないよな。
たぶんメンタルが疲れてる。
わたくし、二十世紀末から四半世紀ほどネットを毎日徘徊しているにわかネット民なんですが、その辺から「目に入った誰かの発言に物申したくて仕方ない」という癖があるという自覚がありまして。その中身は、別に相手の意見を徹底的に否定したいわけでもなく、「そうだよねーわかるー私はねえ」と肯定のように見えて話題を勝手に乗っ取るという、かなり厄介な傾向があります。
「この考え方ヤバいな」と感じている自分もいるので、普段はある程度抑えこんでいる(抑え込んでいるよね?)のですが、何かの拍子にぶわーっと表出するときがある。
自分としてはなんだろな、赤ん坊が目に入ったものとりあえず口に入れてみて試すみたいな、あれに似てるなと思っている。目に入ったもの耳に入るもの、例えば街中の広告とか、となり歩いてる人たちの会話だとか、普段なら脳内で「ないもの」と処理されるのにこの時だけは「あるもの」の箱に片っ端からいれちゃって自動で処理が始まる感じ。最初は気づかないけど気づけば普段以上の負荷がかかって頭がぐるぐると回り出して変になってくる。
そういう衝動、ネットのおかげでWEB日記やブログに書いたりすることで発散していた時期もあるんですが、「それ関わらん方が絶対いいよ」ってやつにも食いついちゃうので、サイクルの速いSNSの世の中とは本当に相性が悪い。
急に「それ」がきたので、その発散と、宣言としてこれ書いてます。数日ネットみません。見ないっつっても数日だけだからネット廃人ほんとよくないよな。
2026年1月29日 この範囲を時系列順で読む
映画「ウォーフェア 戦地最前線」をみてきたよ
映画「ウォーフェア 戦地最前線」をみてきたよ
結構前にな! うだうだしてたら感想書いてなかった。
https://a24jp.com/films/warfare/
こちら、過去にも感想記事を書いた映画「シビル・ウォー アメリカ最後の日」と同じ監督作品です。
予告や紹介文を見ると、まるで「アメリカ兵の困難」が主体の映画であるようにみえるんですが、実際にみていると「急に殴り込んできた外国兵に生活圏がめちゃくちゃにされるイラク人たち」という切り取り方も非常に強い映画でした。まあ実際それはそう。
紹介では「危険地帯」と表現されていますが(それも実際に武装した人たちがいる地域ではあるんだが)、しかして序盤に描かれるのは本当に何でもない住宅街で。
昼には住民が道を行きかい、外では買い物や飲食を楽しむ普通の街の、なんでもない住宅に泥棒のように集団で押し入り、家の壁や扉を勝手にぶちこわし、銃をもって住民たちを閉じ込める様とか、知識では知っていたんですが改めてみるとなんかもうさあ、お前らさあ……という気持ちが自然とわいてくる。すげーなほんと。
この話を作るにあたり、実際に従軍した兵士たちの証言や、イラク側の住民らにかなり細かくヒアリングしたとのことで、つくりとしては限りなくドキュメンタリーっぽいんですが、なんとも不思議なことにバッチバチに「映画」をしています。
わかりやすい波のある展開やドラマ性があるわけではないのに、きれいに三部構成になっている脚本だったり、伴奏や露骨な効果音はないのに完璧な音響設計、現地の立地を完全再現したというのに絵画のように構図の決まった絵作りだとか、きちんと作りこまれた「映画」で舌を巻く。
窮地に追い込まれた兵士の脱出劇というと映画でもよくあるモチーフですが、この映画がすごいのは「窮地に追い込まれて混乱し、心が折れる兵士たち」のリアルなこと。
前作シビルウォーの終盤でもまるで戦場に放り込まれたようなリアルな怖さを実感しましたが、それを全編に拡大した映画というとわかりやすいかも。
鳴り響く爆音、戦友たちの地獄のような叫び声、戦闘に巻き込まれ泣き喚く住民たちの声。呆然とする兵士たちの姿には「最終的には武勇伝」になるような勇猛さはなく、みているこっちが悲しくなるくらい「折れた」としかいいようがない様に居たたまれなくなる。
市民に無礼を働き、一応は国を挙げての目的を持ってやってきたはずの精鋭たちでも「これはもうだめだ」とみているこっちも思ってしまう。
最初に感じた「なんだこいつら、ひどいやつらだ」という気持ちが引っ込んで、「なんなんだこの戦争ってものは」と思わずにはいられない映画でした。
結構前にな! うだうだしてたら感想書いてなかった。
https://a24jp.com/films/warfare/
<極限の95分、映画史上最もリアルな戦場に、あなたを閉じ込める>
2006年、イラク。監督を務めたメンドーサが所属していたアメリカ特殊部隊の小隊8名は、危険地帯ラマディで、アルカイダ幹部の監視と狙撃の任務についていた。ところが事態を察知した敵兵から先制攻撃を受け、全面衝突が始まる。反乱勢力に完全包囲され、負傷者は続出。救助を要請するが、さらなる攻撃を受け現場は地獄と化す。本部との通信を閉ざした通信兵・メンドーサ、指揮官のエリックは部隊への指示を完全に放棄し、皆から信頼される狙撃手のエリオット(愛称:ブージャー・ブー(鼻くそブーの意))は爆撃により意識を失ってしまう。痛みに耐えきれず叫び声を上げる者、鎮痛剤のモルヒネを打ち間違える者、持ち場を守らずパニックに陥る者。彼らは逃げ場のない、轟音鳴り響くウォーフェア(戦闘)から、いかにして脱出するのか。
こちら、過去にも感想記事を書いた映画「シビル・ウォー アメリカ最後の日」と同じ監督作品です。
予告や紹介文を見ると、まるで「アメリカ兵の困難」が主体の映画であるようにみえるんですが、実際にみていると「急に殴り込んできた外国兵に生活圏がめちゃくちゃにされるイラク人たち」という切り取り方も非常に強い映画でした。まあ実際それはそう。
紹介では「危険地帯」と表現されていますが(それも実際に武装した人たちがいる地域ではあるんだが)、しかして序盤に描かれるのは本当に何でもない住宅街で。
昼には住民が道を行きかい、外では買い物や飲食を楽しむ普通の街の、なんでもない住宅に泥棒のように集団で押し入り、家の壁や扉を勝手にぶちこわし、銃をもって住民たちを閉じ込める様とか、知識では知っていたんですが改めてみるとなんかもうさあ、お前らさあ……という気持ちが自然とわいてくる。すげーなほんと。
この話を作るにあたり、実際に従軍した兵士たちの証言や、イラク側の住民らにかなり細かくヒアリングしたとのことで、つくりとしては限りなくドキュメンタリーっぽいんですが、なんとも不思議なことにバッチバチに「映画」をしています。
わかりやすい波のある展開やドラマ性があるわけではないのに、きれいに三部構成になっている脚本だったり、伴奏や露骨な効果音はないのに完璧な音響設計、現地の立地を完全再現したというのに絵画のように構図の決まった絵作りだとか、きちんと作りこまれた「映画」で舌を巻く。
窮地に追い込まれた兵士の脱出劇というと映画でもよくあるモチーフですが、この映画がすごいのは「窮地に追い込まれて混乱し、心が折れる兵士たち」のリアルなこと。
前作シビルウォーの終盤でもまるで戦場に放り込まれたようなリアルな怖さを実感しましたが、それを全編に拡大した映画というとわかりやすいかも。
鳴り響く爆音、戦友たちの地獄のような叫び声、戦闘に巻き込まれ泣き喚く住民たちの声。呆然とする兵士たちの姿には「最終的には武勇伝」になるような勇猛さはなく、みているこっちが悲しくなるくらい「折れた」としかいいようがない様に居たたまれなくなる。
市民に無礼を働き、一応は国を挙げての目的を持ってやってきたはずの精鋭たちでも「これはもうだめだ」とみているこっちも思ってしまう。
最初に感じた「なんだこいつら、ひどいやつらだ」という気持ちが引っ込んで、「なんなんだこの戦争ってものは」と思わずにはいられない映画でした。
2026年1月28日 この範囲を時系列順で読む
アルトネリコWEBオンリー「みんなでモチコミスフィア」おつかれさまでした!
アルトネリコWEBオンリー「みんなでモチコミスフィア」おつかれさまでした!
直前まではいまのアルトネリコ二次創作てどんなもんだろうとドキドキしていましたが、蓋を開けてみれば非常に楽しかったです。
http://newnanbum60.stars.ne.jp/at20th/in...
せっかくだし、本だしたろと一冊ぶちあげました。こちらはいまもPIXIV・個人サイト上で読めます。
https://www.pixiv.net/artworks/140322658
調べてみたら、最後にアルトネリコ同人誌を出したのは10年くらい前でした。確か2020年のコミケスペシャルに参加して出すつもりだったんですが、コロナ渦の影響でコミケが中止となり、それから宙ぶらりんになっていたネタです。もし当時だせていたら5年ぶり新刊だったんでまだ大丈夫。なにが大丈夫なんだ。
今回のイベントでサークル参加者の皆さんが、本当にいろんな形式やメディアで創作活動していて見て回るのも楽しかったです。こういうところはWEBイベントのだいご味だし、アルトネリコの懐の深さだな~と。
枯れ木のつもりでサークル参加してたら、以前からみてますとコメントいただけたり大変恐縮です。いうて自分も全然まだロアルカで活動してると思ってるからね。
写真は会場の一幕から。会場の作りこみがすごかったな~。アバターは一番自分に似てるやつ選んでます。
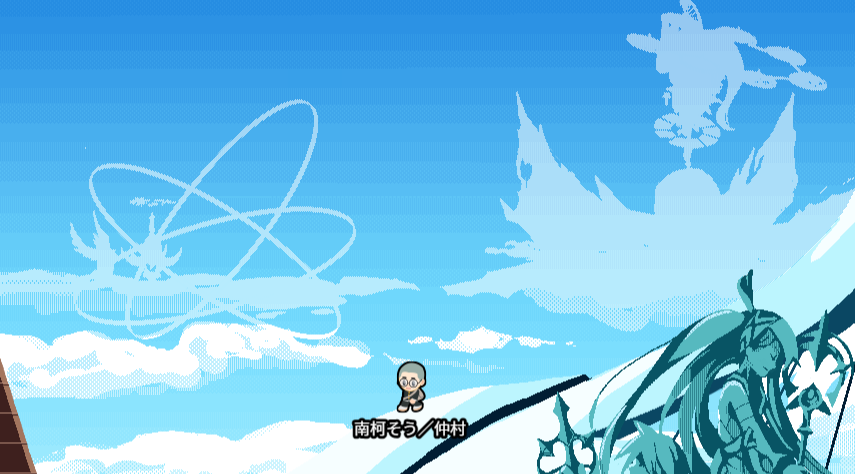
#同人活動
直前まではいまのアルトネリコ二次創作てどんなもんだろうとドキドキしていましたが、蓋を開けてみれば非常に楽しかったです。
http://newnanbum60.stars.ne.jp/at20th/in...
せっかくだし、本だしたろと一冊ぶちあげました。こちらはいまもPIXIV・個人サイト上で読めます。
https://www.pixiv.net/artworks/140322658
調べてみたら、最後にアルトネリコ同人誌を出したのは10年くらい前でした。確か2020年のコミケスペシャルに参加して出すつもりだったんですが、コロナ渦の影響でコミケが中止となり、それから宙ぶらりんになっていたネタです。もし当時だせていたら5年ぶり新刊だったんでまだ大丈夫。なにが大丈夫なんだ。
今回のイベントでサークル参加者の皆さんが、本当にいろんな形式やメディアで創作活動していて見て回るのも楽しかったです。こういうところはWEBイベントのだいご味だし、アルトネリコの懐の深さだな~と。
枯れ木のつもりでサークル参加してたら、以前からみてますとコメントいただけたり大変恐縮です。いうて自分も全然まだロアルカで活動してると思ってるからね。
写真は会場の一幕から。会場の作りこみがすごかったな~。アバターは一番自分に似てるやつ選んでます。
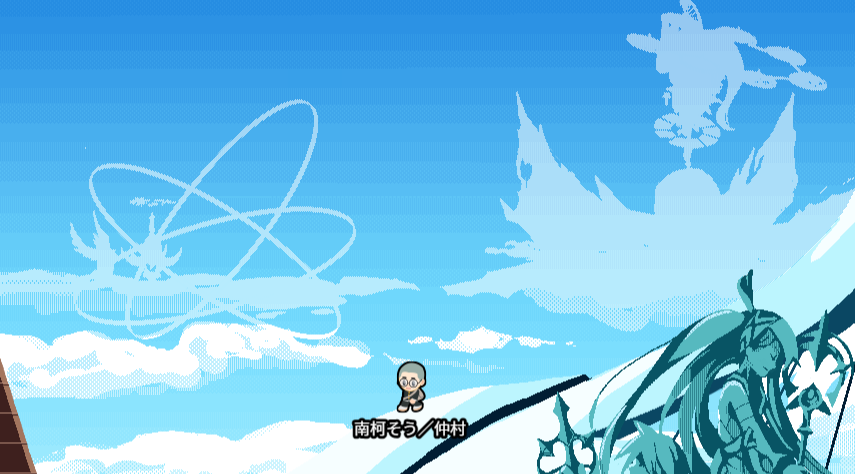
#同人活動
2026年1月22日 この範囲を時系列順で読む
あたまの中身がいっぱいだ
あたまの中身がいっぱいだ
という感じで追い立てられている日々です。
今週末のウェブオンリーの参加準備でどたばたしており、「タスクが積みあがっている」状態が本当に苦手で、普段よりちょっとずつ生活に負荷がかかってる感じがします。イベント前だな~って実感する。
イベント参加といえば自分は1~2月に直接参加することは極力控えているんですが、案の定、地元にドカ雪が降ってます。これがだいたい週末まで続くらしい。この時期は運が悪いと雪で現地に行く手段が絶たれてしまうので、やっぱりこの時期に遠出する前提のイベント参加は厳しいなあと。
足の心配はしなくていいウェブオンリーですが、それでも直前までどたばたするのは現地イベント参加するときと変わらないんだな~って。
そんなわけで私生活について書くことは少ないんですが、近況でした。
という感じで追い立てられている日々です。
今週末のウェブオンリーの参加準備でどたばたしており、「タスクが積みあがっている」状態が本当に苦手で、普段よりちょっとずつ生活に負荷がかかってる感じがします。イベント前だな~って実感する。
イベント参加といえば自分は1~2月に直接参加することは極力控えているんですが、案の定、地元にドカ雪が降ってます。これがだいたい週末まで続くらしい。この時期は運が悪いと雪で現地に行く手段が絶たれてしまうので、やっぱりこの時期に遠出する前提のイベント参加は厳しいなあと。
足の心配はしなくていいウェブオンリーですが、それでも直前までどたばたするのは現地イベント参加するときと変わらないんだな~って。
そんなわけで私生活について書くことは少ないんですが、近況でした。
2026年1月9日 この範囲を時系列順で読む
この世は変わっているけど変わっていない
この世は変わっているけど変わっていない
わたくしのネット人生はだいたい1998年だか1999年ごろ、家にケーブルテレビが導入されてそのついでに定額使い放題ネット回線が開通したのと、家族がノートパソコンを買った時から始まりました。
当時は、パソコン通信やニフティサーブといった総合的コミュニティがネットの中心にあった前時代から、個人がウェブサイトをもって「1国1城があたりまえ」に移行しつつあった時代だった、と先輩方からはうかがっています。自分はその後者の時代の端っこにネットを始めたので伝聞ですけども。
それから四半世紀以上たちぼちぼち30年経つかな、というタイミングなんだけど、ふとした時に「いまって00年代のあのころだっけ」と思う時がある。
自分の人生において、90年代のマスメディアからのオタク叩き、00年代のネット上の女オタク・女叩きというのは、人格形成の年頃真っただ中に受けた「迫害」の記憶・体験であり、いまとなってはあの辺で自分の「他者観」みたいなものが形成されたな~と思う。
歴史家が後年どう判断するかはわからないけれど、ひとつひとつの事象の詳細はことなれど、あの90年代と00年代の事象はひとつなぎだったなと思う。ようは、90年代に周囲から叩かれていた人たちが、自分たちが叩かれた手法をもって別の人と叩いている。「スライドしている」と当時も思った。
なんというか、状況がそろえば「愚かなことを繰り返してはならない」という知性や善性なんてどこかにいってしまって、自分の受けた被害を他者に加害として発揮することなど、当たり前に生じるのだなって。
結構この経験は強烈だったようで、自分は今でも誰かと知り合った時、相手に対して自分が真っ先に思うのは「この人は、あの時の叩きに乗じた(もしくは乗じるような)人か?」と疑った目で見ている。
少しずつ相手のことを知る過程で、だいたいはその印象はぬぐわれるのだが、でも時折、他人のふとした言動の端っこに「あの時、叩いていた人たちの欠片」とでもいうべきものを感じて、「ああ、やっぱりか」と思うこともとてもよくあって。
約20年前と比べて人々の人権意識はどんどん改善されていっていると実感するし、20年前の先進的な考えは今の若い人にとっては「あって当たり前なんだなあ」と思うことも増えたのに、それでもまだしっぽの方にはあいつらがいるのをみて、「変わっていない」とぞっとする。
特に落ちはないんですけど、今年もそう思ったな~っていう記録です。
わたくしのネット人生はだいたい1998年だか1999年ごろ、家にケーブルテレビが導入されてそのついでに定額使い放題ネット回線が開通したのと、家族がノートパソコンを買った時から始まりました。
当時は、パソコン通信やニフティサーブといった総合的コミュニティがネットの中心にあった前時代から、個人がウェブサイトをもって「1国1城があたりまえ」に移行しつつあった時代だった、と先輩方からはうかがっています。自分はその後者の時代の端っこにネットを始めたので伝聞ですけども。
それから四半世紀以上たちぼちぼち30年経つかな、というタイミングなんだけど、ふとした時に「いまって00年代のあのころだっけ」と思う時がある。
自分の人生において、90年代のマスメディアからのオタク叩き、00年代のネット上の女オタク・女叩きというのは、人格形成の年頃真っただ中に受けた「迫害」の記憶・体験であり、いまとなってはあの辺で自分の「他者観」みたいなものが形成されたな~と思う。
歴史家が後年どう判断するかはわからないけれど、ひとつひとつの事象の詳細はことなれど、あの90年代と00年代の事象はひとつなぎだったなと思う。ようは、90年代に周囲から叩かれていた人たちが、自分たちが叩かれた手法をもって別の人と叩いている。「スライドしている」と当時も思った。
なんというか、状況がそろえば「愚かなことを繰り返してはならない」という知性や善性なんてどこかにいってしまって、自分の受けた被害を他者に加害として発揮することなど、当たり前に生じるのだなって。
結構この経験は強烈だったようで、自分は今でも誰かと知り合った時、相手に対して自分が真っ先に思うのは「この人は、あの時の叩きに乗じた(もしくは乗じるような)人か?」と疑った目で見ている。
少しずつ相手のことを知る過程で、だいたいはその印象はぬぐわれるのだが、でも時折、他人のふとした言動の端っこに「あの時、叩いていた人たちの欠片」とでもいうべきものを感じて、「ああ、やっぱりか」と思うこともとてもよくあって。
約20年前と比べて人々の人権意識はどんどん改善されていっていると実感するし、20年前の先進的な考えは今の若い人にとっては「あって当たり前なんだなあ」と思うことも増えたのに、それでもまだしっぽの方にはあいつらがいるのをみて、「変わっていない」とぞっとする。
特に落ちはないんですけど、今年もそう思ったな~っていう記録です。
本文サンプルはこちら
#同人活動