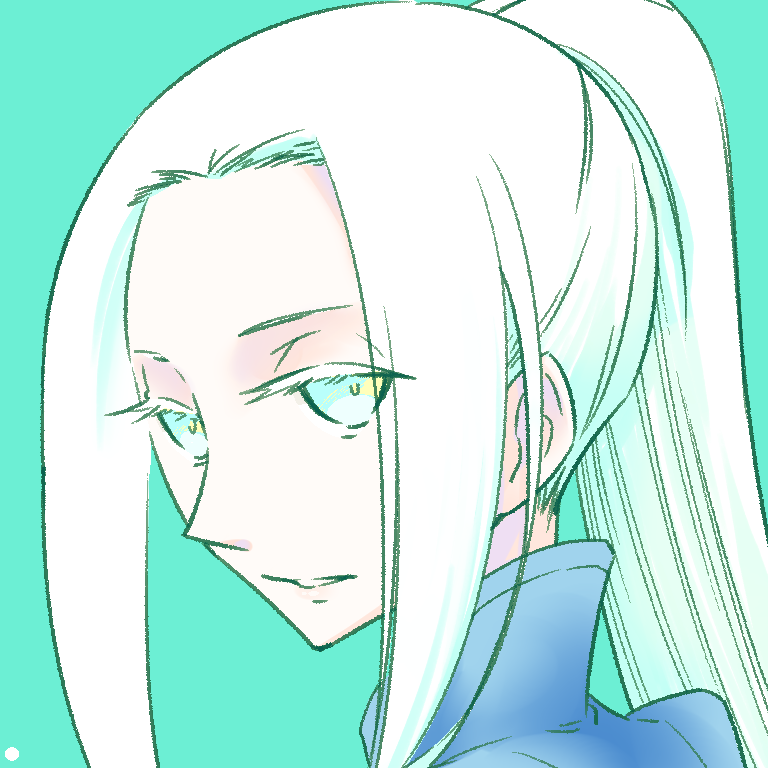2018/06/01
あとがき 続きの続き
ヒロインについては先に決まったというか、これが基点になって全部他も決まって言ったようなものでしたが、主人公についてはヒロインがこうだから隣にいる主人公はこう、というある種の鏡写しのように作っていったキャラクターでした。なので、クルスに関してはメリアという主語が抜けなくてなかなか難しい。
メリアは恵まれた環境で育ったけれど、その恵みは最終的に彼女自身が享受するものではなくて、彼女の嫁ぎ先が享受するもので。なんでしょうね、手間暇かけて育てた果物や野菜を贈り物にするとして、メリアは贈り物そのもので、クルスは一応の宛先です。でもその宛先も、本来は彼個人ではなく彼の一家に宛てたもの。
メリアはそうであることを自覚しながら、そうであることへの最大限の適応を惜しまない人です。クルスはそういう構造だとわかっていながら、人を贈り物として扱うことへの良心の呵責や虚しさはあっても、受け取り拒否したり、受け取ったけど一家に受け渡さないような、そういうことをしないままでいた人です。
作中で彼がメリアを指してあえて「贈呈品」と呼ぶシーンがあります。大した場面ではないんですが、書きながら「この台詞はどうやっても変えられないな」と感じていました。たぶん、彼の人格がまず表出する台詞だからなのかな。
その台詞に象徴されるように、物事と自分に対して斜に構えていてもどうこうできる意欲はなく、かといって諦めや皮肉で処理できない少年が、何かを変えたくて仕方ない動機を持った少女と出会って、変化していくお話が彼の物語なのだろうと。
自分で書いておいて「だろう」ってのも変な言い方ですが、最初からそこを目指したわけじゃなくて、彼と彼女という人格の落ち着くところを探っていたら、その道に乗っかっていた感じ。結果的には典型的なボーイミーツガールじゃんこれ、って自分では思ったけど他から見たらどうかわからん。
クルスの背景に関しては、立場のない、寄り場のない王子という設定をこねているうちに、周りがそうとう変わりました。一番変化したのは冒頭で彼と一緒にいる叔父です。最初は子の人も兄の一人でした。
いずれ権力争いの矢面にされることが決まっている兄弟がたくさんいたら、年少の子はしんどかろう。ついでに兄弟の間でも派閥があればよりしんどいよね。じゃあクルスと兄は立場の弱いほうの派閥で、ごちゃごちゃした経緯で王に嫁いだ母親から生まれたもの同士で。継承権争いでも一目置かれる実力者だが母親の経歴に陰りのある兄と、さして有能というわけでもない弟、そして関係の険悪な腹違いの兄弟たち……という設定だけで一本作れるなーと思ったんですが、そこで一本作れるからだめだよ、これはメリアとクルスの物語だっつの、と考えばっさりカット。
立場の弱い主人公に眼をかける存在として叔父という形に変え、全体のページ数が当初の予定の3倍くらいまで膨らんでやっと終わったことを思うと、変えておいてよかったと思います。
クルスもクルスで大概周囲の事情によって人生と人格が形作られていて、かといってメリアほどそのことを受容できているわけじゃなく、自分と同じような人生をみつけると複雑な心情になる。それは一転して情け深い性格なのではないかなあと、それをちゃんと表現してあげたいなと思って描いてました。
あと、それはそれとして、自分らに実害を及ぼす輩にはぶん殴り返す気概もある。味方には情け深く、敵には容赦ない。物語の主人公ならいかんせん動いてくれないことには困るので、動機の持ち方はシンプルです。
チッタとフェルムとの関係は、(作中でもちょっと触れてますが)フェルムは田舎貴族の四男坊で、チッタは本来彼の従者でした。そういう階級が集う学校に2人して通ってたんだけど、その間に「空白期間」のクルスと町で出会い……という流れ。クルスにとっては一番辛い時期に出会った友達です。メリアはトリフィと出会うことで己の中でひとつの指標が生まれましたが、クルスにとってもチッタとフェルムは近しいものがあったんじゃないかと思っています。
クルス本人は、いまも周囲の影響を受けてぐにゃぐにゃと変わるようなところがあるので、掴みやすいようで掴みづらい。物語に奉仕するための存在ですけど、でも彼がいないとこの物語は生まれない。
クルスは他人から「メリアのことどう思ってるの」と聞かれたら「顔がいい」と返すと思います。内心では、彼女の生き方をすべて肯定的に見ることはできないけど、最大限の敬意を払おうと思っているし、助力は惜しまない。
ただ、メリアの伴侶に対して奉仕を惜しまないところは「ちょっとアレ」って思ってる。メリアのほうは伴侶が誰であっても同じことをするわけではないんですけども、それはたぶんまだよくわかってない。クルスのそういうとこは周囲から「ちょっとアレ」って思われてる。
男女の関係というと、どういうジャンルのどういう地域の作品でも、現代においては「対等」というキーワードが重要だと思うんですが、この2人に関しては「どこかを対等にしようとすると、かえって歪む」という感覚がありました。特に婚姻関係を結ぶとなると、どうやっても故郷や生まれ育った家庭から離れて暮らす人と、それを受け入れる人とでは社会的立場や地理的な優位性は違ってくるし、そこに安易に手を加えて「対等でござい」とやっても面白くなる予感がしなかった。
なにやったって二人の溝は埋まらないなら、その溝があることを面白さにできないやろかということは、全編にわたって考えていたことです。二人の間に溝があるねってことは認めても、安易にそれを埋めても頑丈で平らになると限らないし、じゃあちゃんと埋めるにはどうすれば、埋めなくてもちゃんとするにはどうすれば? ちゃんとしないならどうなるかしら? ということを考えるほうが物語的に面白くなるのかなあと、1本丸々描いてみえた方向性です。
何はともあれもう少しぐるぐるしてみようと思います、この物語について。